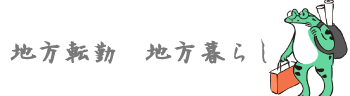今ではすっかり存在が忘れられているが、かつての郡は現代でも人々の生活に一定の影響を及ぼしている。たとえば県民体育大会などでは、旧郡域をもとにチームが分けられるのが常である。
ところでその郡域には大小あるが、一般論としては大きな郡が存在するのは都から遠隔の地が多い。
陸奥国閉伊郡とか日向国諸県郡などが代表例である。
例えば明治初期までの諸県郡は、現在でいえば北はえびの市から南は曽於郡大崎町にまで及び、その中に小林市、都城市、高原町、三股町、国富町、綾町、宮崎市の一部、志布志市を含んでいた。
人口希薄でありながら行政区域が細かく分割されているのは、行政コストの観点から不利であるので、人口希薄な遠隔地ではどうしても広くなる。
日本に限らず、戦国時代の中国を見ても、ヨーロッパ諸国を見ても、人口稠密な中心地では国が細かく分割される一方で、人口希薄な遠隔地では広大な国家が現れる。
たとえばロシアのように。
辺境の地に狭い郡が密集している地域
ところが、こうした原則に逆らうように、決して人口が多かったと思えない薩摩半島の尖端には狭小な郡がひしめいていた。それらを北から並べると以下のようになる。
鹿児島郡(現在の鹿児島市中心部)
谿山郡(鹿児島市南部)
給黎郡(鹿児島市喜入と南九州市知覧)
揖宿郡(指宿市の大部分)
頴娃郡(南九州市頴娃と指宿市の一部分)
明治22年の市区町村編成法が成立した時点で、鹿児島県は鹿児島市と各村から成っていた。
町は無かった。
このことからも、これらの地区が決して人口稠密な地域ではなかったことがわかる。
市こそなかったものの町が4つ存在した宮崎県(延岡町、細島町、宮崎町、都城町)には伝統的に広大な5郡(臼杵郡、児湯郡、宮崎郡、那珂郡、諸県郡)しかなかったのと対照的である。
なぜだろう。
以下、本稿は全て想像であるので、そのつもりで読み進めていただきたい。
問題の諸郡が海岸沿いに一列に並んでいるは、海から人が来たことを想像させる。
陸伝いなら、すべて鹿児島郡であったろう。
だとしても、それらが統合されずに小さい郡のまま残っていたのはなぜなのか。
まず、大和朝廷に征服された時点で多数の小勢力が存在していたとすると、この地域への殖民は、そう古くないのではないかと想像される。
時を経れば、その中で優勢な勢力が他を圧倒し、征服するだろう。
然る後に大和朝廷に征服されれば、それなりに郡域は広くなるはずだ。
全国的に見れば、近畿地方のような人口稠密地域を除けば郡の面積はもう少し広いのだから、当時の行政技術ならばもっと少し広い勢力を維持できたはずだ。
縄文後期に火山の噴火で南九州の人類がいったん絶滅したという説があるようだがあるいはそれ以後の殖民なのかもしれない。
さらに想像をたくましくするならば、各郡の郡民は、出自が互いに全く違うのではないだろうか。

郡は古代豪族の勢力範囲である。
もしもこれら各郡が、互いに言葉も違い、文化も習俗も違う異民族どうしだというのならば、大和朝廷による征服後も、たとえ人口希薄であっても小単位のままで統治するのもやむを得ない。
海から来た人々
この地域は、海を渡ってきた勢力が最初に定着する地域だったのではないか。
距離からいえば大隅半島の佐多岬のほうが薩南諸島に直接に接続しているが、大隅半島の尖端部には薩摩半島のような平地が乏しく、大規模な定住には適さない。
いわば日本の海の玄関口だ。しかし裏口である。
三国志(魏志)に記載されている倭国への経路は朝鮮半島経由であった。
したがってこれが中国から見た正規の経路である。
余談だが、博多周辺にも伊都郡、志摩郡といった矮小な郡が存在した。
日本の表玄関は博多であって、後漢から下賜された金印も博多湾に臨む志賀島で発見されている。
したがって、薩摩を入口として入ってくる民族は、少なくとも中国中原の政府とは無関係な、あくまで非公式な移民である。
もう一つ気づくのは、薩摩に入ってくる民族は、相当高度な航海術と地理の知識を有していたはずだということだ。
「見える陸地」を伝って来れる朝鮮半島経由の経路とは異なり、南西諸島経由では、宮古島と沖縄島の間がかなり離れている。
(まったく見えないかどうかはわからないが)
そして小なりといえども集落を形成できるような移動は、決して漁中にシケに遭うなどといった偶然では起こらない。

(南西諸島有数の巨島、石垣島)
想像してほしい。たかだか数人が海岸にたどり着いたとして、どうやって集落を形成できるほどに成長できるのか。
少数で漂着して原始的な生活を開始しても、近隣の勢力に征服されて終わるだろう。
もしも自分がそうした立場に立ったならば、独立など大それたことは考えずに、近隣に既成の集落を探して助けを求めると思うがどうなのか。
可能性が絶無とまではいわないが、偶然の漂着を主因として、同時にいくつもの小勢力が成長するなどということは考えにくいのだ。
大人数での計画的な移住
やって来たのは、集落を拓くのに必要な土木工事や食用の動植物の知識、あるいは栽培植物の種などを持参する多数の職人を抱えた集団であったはずだ。
そもそも、男性と女性がいなければ子孫も残せないではないか。
これは集落単位の、ある程度計画的な移民である。
その人々は、宮古島の遥か先に、見えはしないけれども大きな島があることを知っていた。
そして、あるいはその多くが海の藻屑と消えたのかもしれないが、いくつもの集団が「見えない島」へ向けて決死の船出を試みたのだ。
かなり後の世のことになるが、倭の五王は中国の南朝と通交しており、そのルートは南西諸島経由以外にはありえない。
朝鮮半島経由では、南朝と敵対する北魏の領域を通過しないと南朝の首都建康には辿り着けないのだから。
このことから、紀元後数世紀の段階ではすでに近畿の朝廷でも南西諸島経由の航路を知っていたことがわかる。
では、それほどの人口と知識と航海技術を有しており、しかもあえて定住せずに新しい天地を求めようというのは、いったいどこの誰なのか。
そういう集団は複数おり、なおかつ中国政府の正式な殖民ではないのだ。

(大隅半島から見た指宿と開聞岳)
候補の一つは海賊である。長江河口域は後世にわたって海賊の根拠地であって、彼らなら過去の偶然の積み重ねから、南西諸島経由の航路を知っていても不思議ではない。
だが、彼らには動機がない。
殖民が可能であるのは無人の土地が広がっているからであって、そうしたところにわざわざ海賊業を働きに行きはしないだろう。
あるいは食い詰めて故郷を脱出した集団があったのかもしれないが、そうした人々はむしろ高価な船で遠洋に乗りだすよりは、陸路を彷徨うものと思われる。
なぜならば外海の波浪をしのぐ屈強な船は用意できないだろうからだ。
つまり、殖民してきた集団は資産家であったはずだ。
命の危険を冒してまで新天地を求めなくてはならない資産家とは誰なのか。
故郷を失う人々
弥生時代がスタートしたとみられる紀元前4~3世紀というのは、世界的には大異変があった時代である。
マケドニアのアレクサンドロス3世が、ペルシアを征服した。
ペルシアは世界一の超大国であった。
まるでそれに呼応するかのように、インドではマウリヤ王朝が急に強盛となってインド亜大陸の大部分を征服し、続いて中国ではわずか10年の間に秦が六国を滅ぼして、史上初の統一王朝を樹立した。
これにはペルシアの亡命貴族の影響が推察される。
彼らが、最先端の政治・軍事技術やその他の技術を伝えたのだ。
戦国七雄の中では最も辺境に位置し、半ば夷狄とみなされていた秦だが、その位置は中国の中では最もペルシアに近い、いわば西への玄関口である。
後世のサーサーン朝がアラビアに滅ぼされた際にペルシア貴族たちが唐に亡命してきたように、アレクサンドロスに追われたペルシア人が同様にインドや中国に亡命していたとしても不思議はない。
世界で最も豊かな国の貴族たちは、多くの一族、配下や職人を抱えていたことだろう。しかも彼らは故郷を失っている。
その亡命先はインドと中国だけなのか。
さらに、インドや中国で初の統一王朝ができたとすれば、それらの地でも、やはり多くの亡命貴族が発生したはずだ。
彼らの大部分は新しい主人に仕えただろうが、それで貴族の待遇や旧来の権利、領地が保証されたとは限らない。
身を屈するを良しとしない一団もいたかもしれない。

幸か不幸か、当時南九州には先住の人類が滅亡して、無人の地になっていた。
大和朝廷、そして熊襲
本稿の主題はこれで終わるが、なお関連して2つの問題について考える。
それは高天原伝説についてと、熊襲についてだ。
日本の開国伝説というのは、かなり妙な構成になっている。
明らかに僻地である九州のどっかに天から降ってきた神様の子孫が、あえて故郷を捨てて東方に勢力を築き、かつて自分が降り立ったはずの地に蟠踞する異民族を征服することになっている。
一般に、これは「加上の法則」と言って、新しく征服した民族の伝承が自分の民族の伝承の一番古い伝説のさらに前に追加されるという現象の一例だと理解されている。
しかし実際に、九州から東に遷って、その後に九州を征服するという現象がありえないわけではない。

(霧島の高千穂峰。宮崎県の高千穂峡と並び、天孫降臨伝説がある)
天から降ってきたというのは、要するに外国から来たということだろう。
南九州から来たということは、非正規の移民、つまり亡命集団の中で遅れてやってきた者たちだと推測できるが、九州に着いた時点では、既に既存の勢力があり、結局、定着して成長することができなかった。
だから、再び新天地を求めて東への移動を始めた。
東日本には縄文人が住んでいる。
長い航海を成功させる技術を持った彼らのことだ。縄文人を征服することなど苦でもなかったことだろう。
多くの従属民を獲得して、勢力は急速に成長したはずだ。
だとすると、彼らが東方で勢力を蓄えた後に対決した南九州の雄、「熊襲」とは何者なのか。
熊襲とは、本来「ソ」のことであると聞いたことがある。
ここに噌唹郡という郡がある。口編がついているのは、異民族に汚い字をつける中国式の命名法に倣ったものだろうから、本来は「曽於郡」であろう。字面から彼らが異民族と見做されていたことがわかる。
日向国の都於郡を「とのこおり」と読む例に倣えば、曽於郡は「そのこおり」であろう。つまり彼らの民族名は「曽」である。
日本語に馴染まない一文字名は、彼らが中国から渡来したことを予想させる。
曽とは熊襲のことなのだろうか。
その支配領域は広く、古くから定着に成功していたことを予想させる。
もしも熊襲が曽で、たとえばそれが楚のことだとしたならば。
大和朝廷が対峙していたのは蛮族などではない。
高度な文明を保持する恐るべき強敵であったことになる。
神話としては、日本武尊は熊襲を軍事力でねじ伏せることができず、女装してその王に迫るという奇策を用いて征服を成功させたことになっている。
ただし、当時の日本語での「曽」が、中国語で発音される「楚」と近い音であったのかはわからない。違えばこの空想は根底から瓦解する。
最後に。
本稿の根拠は、ただ「僻遠の地に狭い郡が連なっている」というだけである。
あくまで個人の想像であることを重ねて申し上げておきたい。